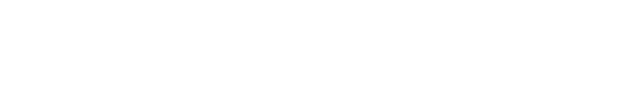降圧薬って、朝飲んだ方がいいの?それとも夜?
血圧の薬を飲んでいる患者さんから、よくいただく質問のひとつがこれです。
「毎朝飲んでるけど、夜のほうが効くって聞いたけど…」「朝の血圧が高いから、就寝前に飲んだほうがいいのかな?」
実はこの「降圧薬は朝か夜か?」というテーマは、世界中で長年にわたって研究と議論が続けられてきている分野です。いくつもの研究が行われてきましたし、日本や海外のガイドライン(ガイドラインとは診断や治療について、どうすればよいのかの指針を記したもの)も定期的に更新されています。
この記事では、最新の知見にもとづいて、「いつ降圧薬を飲むのが良いのか?」について、専門的な話をかみくだいて分かりやすくご紹介します。
日本と海外のガイドラインではどのように言われているか
日本(JSH)と海外(ACC/AHA、ESC/ESH)の高血圧ガイドラインでは、降圧薬の「いつ飲むか」について厳密な決まりはなく、次のような共通した考え方が示されています:
-
毎日決まった時間に服用することが大切であり、「朝に飲む」「夜に飲む」のどちらが優れているとまでは言えない。
-
患者さんが服用を忘れにくい時間を選ぶことが、治療を長く続けるために重要。
-
特別なケース(早朝高血圧、夜間高血圧など)を除き、服用のタイミングよりも血圧が1日を通して安定していることが最も重視される。
たとえば、日本高血圧学会では、服薬時間に関する明確な推奨はせず、「モーニングサージ」などがある場合には医師と相談のうえで調整することが記されています。また、欧州ESCガイドラインでは、「夜に飲むべきという信頼できる証拠はない」と明言しており、朝・夜どちらかに固定して飲むというよりは、患者個人に合わせた柔軟な服薬指導が重視される流れです。
臨床研究の結果
-
Hygia Chronotherapy Trial(2020年) – スペインで行われた大規模試験(約19,000名)では、降圧薬を就寝前に服用した群で心血管イベントが大幅に減少したと報告されました(心血管死・心筋梗塞・脳卒中などの発生率が約45%減少)
-
TIME試験(2022年) – 英国の大規模試験(約21,000名)では、朝飲む群と夜飲む群で心血管イベント発生率に有意差はなく、服用時間に関わらずイベント発生率は同等でした。
-
BedMed試験(2024年) – カナダの一般高齢者や要介護高齢者を対象とした試験でも、朝服用群と就寝前服用群で大きな差は見られませんでした。
以上のように、最近の大規模RCTでは「服薬時間による明確な差は認められない」との結果が相次いで報告されています。
朝の血圧上昇(モーニングサージ)と夜間高血圧と服薬タイミング
朝方の血圧急上昇(モーニングサージ)は、起床後の交感神経活動の高まりによって起こり、心筋梗塞や脳卒中のリスク上昇に関連するとされています。夜間高血圧は、就寝中に血圧が下がらず持続的に高い状態で、心血管イベントリスクが高いことが知られています。睡眠時無呼吸症候群などが背景にあることも多く、24時間血圧測定で診断を確定します(当院では機器がなく検査することはできません)。これらリスクを下げようと、あえて就寝前に降圧薬を服用する考え方も一部にあります。しかし前述の研究結果では服薬時間による差は示されておらず、服用時間は患者の都合に合わせてよいとされています。現在は「朝の血圧が高い」「早朝に症状が出やすい」場合でも、まず家庭血圧の時間による測定結果や生活習慣を踏まえて服薬タイミングを患者さんごとに合わせて当院では提案しています。
まとめ
現時点では「降圧薬の服用は朝でも夜でも、服用時間による決定的な心臓や脳の病気のトラブルの差はない」というのが国内外の最新の見解です。したがって、服薬タイミングは患者さん自身の生活リズムや習慣に合わせて選び、毎日続けられる時間帯にすることが現実的な対応とされています。ただし、糖尿病や慢性腎臓病などを伴う場合、あるいは極端に早朝高血圧が著しい場合など、一部の特殊なケースでは最適な服用タイミングが異なる可能性も否定できません。最終的には、患者さん一人ひとりが自身の生活習慣や体調に合わせて、主治医と相談しながら服用時間を決めることが重要と考えています。
参考文献:jpnsh.jp, cardioaragon.com, aafp.org, aafp.org, escardio.org