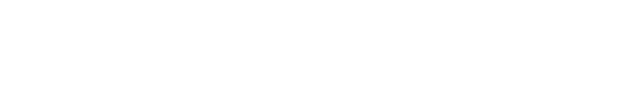「期外収縮がありますね」と言われたら読む記事
期外収縮とは
心臓は右心房にある「洞結節」という部分がペースメーカーとなって規則正しく電気信号を作り、心房→房室結節→心室と伝わることで拍動しています。
期外収縮は、この正常なリズムの間に「異常な場所から早いタイミングで電気信号が出る」ことで、いつもとは違うテンポで心臓が収縮する現象です。
心臓の上(心房)から出るものを「上室性期外収縮(PAC)」、下(心室)から出るものを「心室性期外収縮(PVC)」と呼びます
いずれも健康な人にも起こりますが、心筋症や狭心症などの基礎心疾患がある人では多く見られます。例えば、上室性期外収縮は単独なら危険性は低いとされていますが、加齢とともに増え、頻回だと将来の心房細動(脳梗塞リスクがある不整脈)のきっかけになる可能性があります。
心室性期外収縮も構造的心疾患がなければ予後良好ですが、連発して出現したり非常に多い場合は注意が必要です。
症状
多くの場合、無症状で経過しますが、症状がある方は、以下のような表現をすることが多いです。
・脈が飛ぶ感じ
・ドクンと一瞬大きくなる
・胸がドキンとする
・胸の違和感があるが、ほんの一瞬
・夜や横になっているとき、静かな時に症状を感じやすい
・まれに胸苦しさや息切れ、めまいを自覚することもあります
期外収縮を増やす誘因
-
ストレス・疲労:精神的・肉体的ストレスや睡眠不足は発作を誘発しやすいです
-
カフェイン:コーヒー・紅茶・エナジードリンクなどの過剰摂取
-
アルコール・喫煙:お酒の飲みすぎや喫煙も期外収縮を増やす要因です
-
過度な運動:急激・激しい運動は心臓に負担となり、期外収縮を起こしやすいことがあります
十分な休養・睡眠やリラックスを心がけ、カフェインやアルコールは控えめにするなどの生活改善で症状が軽減することがあります。食事中に増えたり、明らかな誘因がないことも多々あります。
検査の内容
期外収縮の診断と評価には以下の検査を当院では行います。
-
標準12誘導心電図:最初のスクリーニングで期外収縮を見つけますが数秒のリズムしか見れない為正常となることもあります。
-
24時間ホルター心電図:日常生活での心拍を24時間連続記録し、期外収縮の頻度・出現タイミング・連発の有無などを評価します。症状と期外収縮の一致を確認するためにも有用です。
-
心エコー検査(心臓超音波):心臓の壁や弁の構造的異常を調べる検査です。心室性期外収縮では心筋症や弁膜症の有無を、上室性でも長期間多発している場合に心機能への影響を確認します。
-
胸部X線検査:胸部X線で心拡大の有無を確認し、心臓への負担なども考えます。
-
血液検査:血液検査では甲状腺機能異常や電解質異常などを調べます。
以上の検査で異常がなければ、多くの場合特別な治療は不要となることが多いです。
治療が必要な場合
期外収縮が単発で軽度であれば基本的に治療の必要はなく様子をみます。しかし、以下の場合には治療や精密検査を検討します。
-
症状が強い場合:日常生活に支障が出るほどの激しい動悸や苦痛を感じるときは、薬物治療で症状を緩和します。
-
頻度が非常に多い場合:24時間ホルター心電図で1日あたり100回以上の上室性期外収縮で心房細動の発症リスク、1日あたり10,000回以上の心室性期外収縮が出る場合は心機能低下のリスクが高まることが知られています。
-
連発:連続して期外収縮が続く(3連発など)場合も要注意です。
-
基礎心疾患の有無:狭心症、心筋症、心筋梗塞などの病歴があれば、期外収縮が心疾患の“悲鳴”の場合があります。この場合は不整脈そのものではなく、元の心疾患の治療が優先です。
よく健康診断などで指摘される、無症状の期外収縮(精査で心臓の疾患を伴わない場合)では、ガイドラインでも「積極的な治療は通常推奨されない」とされ、定期的な経過観察が勧められています。しかし、症状がある場合はβ遮断薬などで動悸を和らげる治療を行います。
まとめ
無症状で検査で問題がない期外収縮では積極的な治療や検査は不要です。
一方、症状が強い場合や頻度が多い場合は、β遮断薬やCa拮抗薬で負担を減らす治療が必要です。カテーテルアブレーション(カテーテル治療)は、回数の多い心室期外収縮で心機能低下が懸念される場合や薬剤で症状が改善しない場合などに適応となることがあります。
当院では、健康診断で指摘された期外収縮や脈が飛ぶ、一瞬ドキッとするような症状まで期外収縮が診断された方や疑われる方の、検査や治療を積極的に行っています。気になることがあれば当院までお問い合わせください。